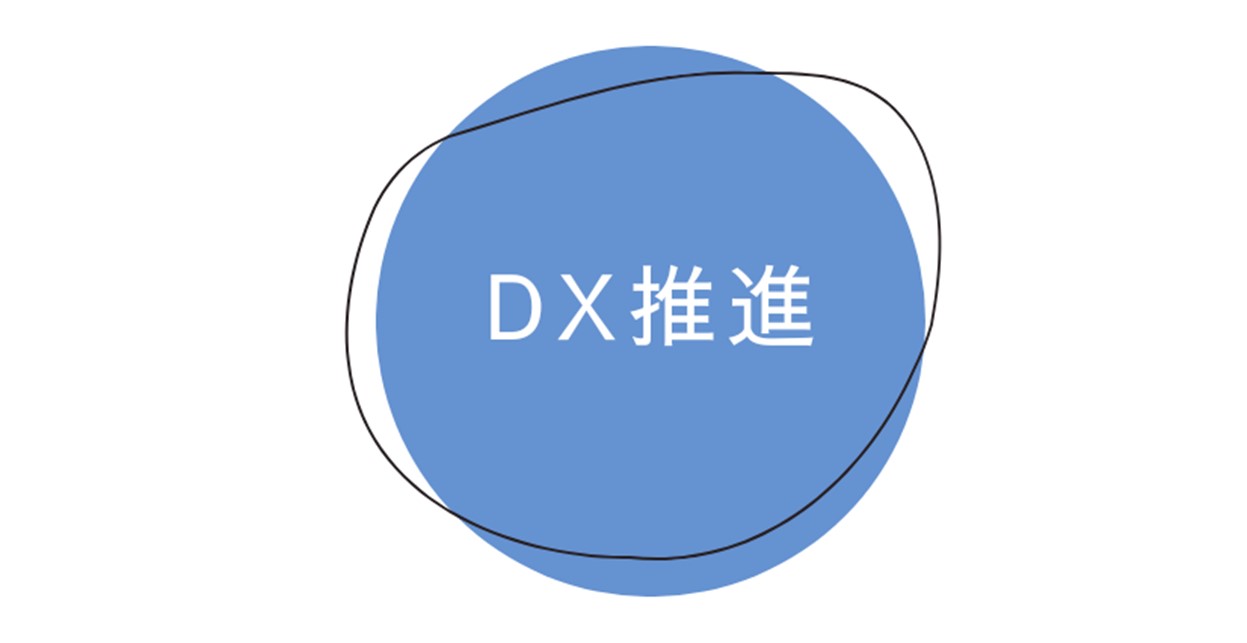
全体最適と部分最適——業務改善のバランスを考える
赤嶺 奈美
DX推進業務改善に取り組むとき、つい最初から最後までの工程をシンプルでスマートなものに変えたくなるものです。
理想的には、それが最も効率的な方法でしょうし、できるかもしれません。
しかし、現実には、普段の業務を行いながら、新しい業務フローのテストを繰り返し、最適な形を見つける必要があります。
さらに、その変更が他の業務や職員に影響を与える場合、調整作業は一層複雑になります。
業務改善の第一歩は「目的の明確化」
業務改善のスタート地点は、まず「何を完成させるのか?」を明確にすることです。
目的や完成品をはっきりさせたうえで、現在の業務フローにある無駄を見つけていくことが重要です。
しかし、「無駄」に見える作業が本当に不要なのかを慎重に見極めなければなりません。
なぜなら、手間がかかると思われていた作業が、実はミス防止や品質確保のために必要なプロセスであることも少なくないからです。
全体最適と部分最適の視点を持つ
業務効率化を進める際は、以下の視点が必要になります。
- 本当の無駄なのか?
→ その作業をなくすことで、逆にミスが増えたり、重要な工程が抜け落ちたりしないか? - 自動化できるか?
→ 人の手を介さずに処理できる部分はどこか? - どのタイミングで人の判断が必要か?
→ どこで人間の意思決定や責任が求められるか?
全体と部分、両方を見据えた柔軟な改善を
業務改善は、「全体の流れをスムーズにする全体最適」と「現場の働きやすさを高める部分最適」のバランスが鍵です。すべてを一度に完璧にする必要はありません。小さな改善を積み重ねながら、目的に向かって段階的に進む姿勢が大切です。
「本当に不要な作業は何か」「どこに人の判断が必要か」を丁寧に見極め、現場の声にも耳を傾けながら、柔軟な発想で業務フローを見直しましょう。
業務改善は、一時的なプロジェクトではなく、継続的な試行錯誤のプロセスです。大切なのは、現場で実行しやすく、続けやすい改善を積み重ね、最終的に全体の最適化につなげることです。
「部分から全体へ」――その積み重ねが、組織全体の成長につながります。
2025年3月10日
著者紹介
- DX推進支援部 ICT活用推進課
最新の投稿
- 2025年3月26日DX推進全体最適と部分最適——業務改善のバランスを考える
- 2025年3月25日DX LAB KTQ【DX LAB KTQ】地域DX共創活動最終発表会開催のお知らせ
- 2025年3月5日DX推進AIを活かすために、まず情報を共有しよう
- 2025年2月21日DX推進ツールは選び方より使い方――業務に合わせた活用法とは?


